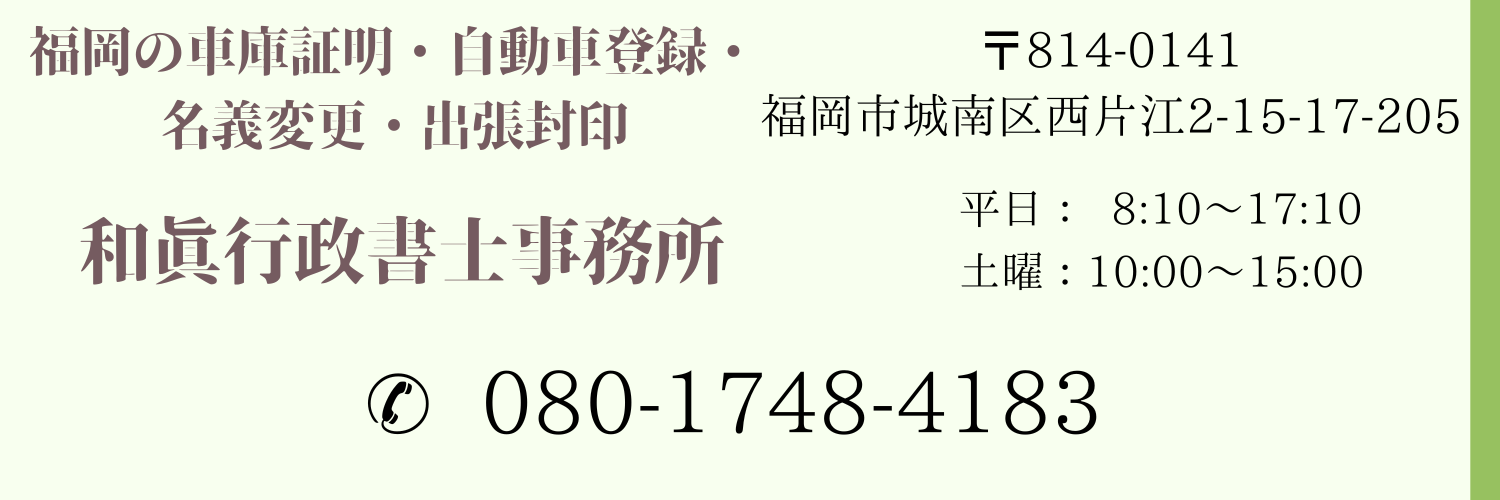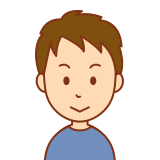
行政書士試験の中にある、記述式ってどんなものなんでしょうか?
概要を知りたいです。
今回は記述式の概要について紹介していきます。宅建や社会保険労務士試験などと違って、択一式の他に行政書士試験には記述式というものが入ってきます。
これから行政書士試験の勉強を始める前の方にとっては、記述式と聞くとなんだか難しいものなのではないかと感じるかもしれません。私も最初はそうでした。
しかし今回記述式についての概要を頭に入れることで、しっかり記述式の勉強に向き合うことができます。
それでは説明を始めていきます。
行政書士試験記述式の概要
点数・配点
まずは行政書士試験における記述式の配点を紹介します。
試験全体の20%を占める、重要な部分と言えます。もし記述抜きで180点を目指すとなると、240点中180点とかなりハードルが上がってしまいます。
出題数
続いて出題数です。
これは毎年決まっています。行政法は1問のみで、民法は2問の出題です。民法が2問の出題なのでここでコケると不合格に近づきます。民法は択一式はもちろん、記述式も大事ですね。
出題内容
続いてこれまでに出題された問題の内容を紹介します。
行政法
- 一般的な法理論…3問
- 行政手続法…2問
- 行政不服審査法…出題実績なし
- 行政事件訴訟法…8問
- 国家賠償法…出題実績なし
- 地方自治法…1問
行政法の出題は、かなり偏りがあります。行政事件訴訟法は毎年警戒しておかなければなりません。試験委員はどうやら大好きな分野みたいです。
ただしたまに裏切って、地方自治法というカードをきってくるパターンもあります。全範囲出てくると考えて、まだ出題のない行政不服審査法・国家賠償法の部分も注意しておきましょう。
民法
- 総則…3問
- 物権…6問
- 債権…16問
- 相続・家族法…3問
民法では圧倒的に債権法から出題されます。毎年1問は債権法からの出題と考えて間違いありません。おそらく試験委員は債権法の分野も好みなんでしょう。債権法から2問出題という年度もあったくらいです。
オーソドックスなものは物権+債権という組み合わせでしょう。ただ忘れた頃に相続・家族法なんかが出てきますので、そちらの対策も抜かりなくしておく必要があるでしょう。
まとめ
今回は行政書士試験における記述式の大まかな概要について紹介しました。記述式がどういう位置づけで、どのような分野から出題されがちなのかというのがわかったのではないでしょうか。
次の記事で記述式について、記述式の採点の注意点について書いたので読んでみてください。
行政書士試験 記述の採点は年によってなぜばらつきがあるのか?
記述式のまとめ記事はこちら↓↓↓↓